こんにちは!ほうかごEnglishインターン生の あかり です。
前回、私がNZの学校で受けたESOLの授業レポートの第1弾として、中学校(Year7-8)のESOL授業の内容を紹介しました。
NZのノンネイティブ向け英語の授業ESOL、実際はどんなもの? その1
今回は、高校のESOL授業(Year9-10)とESOL卒業後(Year11以降)の授業について紹介します。
ESOLとは、English for Speakers of Other Languageの頭文字を取ったもので、英語を母語としない生徒のための英語クラスです。
ESOLは学校や生徒の英語力によって授業内容が異なるため、このブログ記事は一例として参考になればと思います。
NZの各学年が日本の何年生にあたるかについては次の記事をご覧ください。
ニュージーランドの教育システムとその特徴…日本の教育制度と何が違う?日本から留学する際のポイントとは?
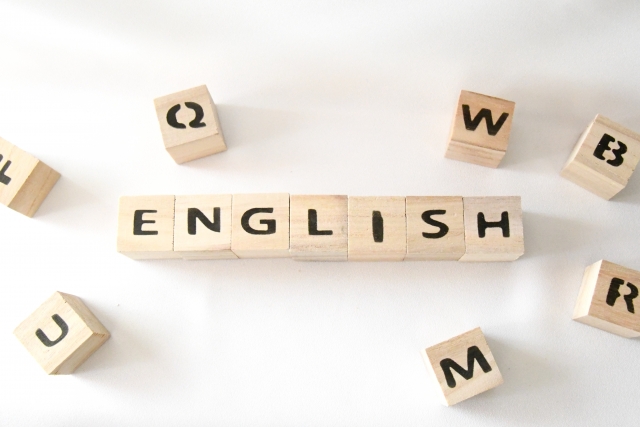
Year9
NZは中学校は2年間(Year7&8)で高校が5年間(Year9~13)なので、Year9から公立の高校に通い始めた私ですが、まだまだYear9に必要とされている英語力には届いておらず通常の英語クラスに加えてESOLのクラスも受けます。
高校になると中学とは時間割のシステムがガラッと変わり、ESOLは言語学習のクラスのひとつになり、何かの授業を抜けるのではなく、ネイティブスピーカーが第二言語のクラスで新しい言語を学ぶ代わりにESOLのクラスで英語を勉強します。
私の高校は生徒数が多い高校だったためESOLのクラスがレベル分けされていて、上のレベルから順にESA, ESL, ESRと分かれていました。ESOLのクラスのレベル分けは高校入学前の英語テストの結果で振り分けられます。Year9のネイティブスピーカーが必須とされている単語数や文法知識などが基準になっているらしく、学期ごとに単語テストとライティングテストがあり、その結果に応じて次の学期のクラスが変わったりESOLを卒業することもあります。
私は1学期にESLのクラスになり、一年間同じクラスでした。
先生は学校のESOL担当の先生で、クラスは15人程度だったと思います。中学の時とは違いしっかり座学での英語勉強を行ってました。
学校が指定するESOLの教科書(A4サイズ、200ページほど)を購入してそれを使って授業が行われてました。この教科書の中に単語集があったのですが、その単語集から毎週20単語を覚えてスペリングの小テストがありました。中学のESOLではスペリングはリーディングや文法など他のスキルの勉強の中で学ぶ感じでしたので、スペリングがとても苦手でした。そのため高校のESOLではスペリングに苦戦しました。また長編小説を読み、それについてエッセイを書いたりと通常の英語クラスとほぼ同じ課題を先生からのサポートが多めで少しゆっくりなペースで進めることもありました。エッセイの書き方の授業やエッセイを書く中で頻出した間違いを元に文法の授業が行われたりと各クラスに合わせた進め方でした。
ESOLと同時並行で通常の英語のクラスの授業も受けていました。基本的には授業についていくのには問題なかったのですが、日本での古文漢文にあたる“シェイクスピア英語”は意味がさっぱり分からず。高校で5年間勉強しましたが、未だにシェイクスピア英語はよく分かっていません(笑)
Year10
Year10のESOLクラスもESA, ESL, ESRに分かれていました。Year10ではESOLの中で1番上のESAのクラスになりました。この時点では授業も含め日常生活で英語に困ることはあまりなかったです。Year10のESOLも内容はYear9とほぼ同じで、英語が1学年分レベルアップした感じでした。
Year10の時のESOLのクラスではクラスメイトの仲が良く、このクラスで仲良くなった友達とは今でもよく一緒に遊びます。私にとってESOLはただ英語の勉強をするだけでなく、自分と同じような境遇の子たちと知り合って仲良くなる機会でもありました。
そしてYear10の年度末の単語テストとライティングテストの成績がESOLを卒業できる基準に達したためYear10でESOLは終了しました。
ESOL終了後(Year11以降)
Year10でESOLを終了した私はYear11では通常の英語クラスで英語を学びました。授業中に英語が分からず困ることはほぼ無いものの、課題(特にライティング)を進めるスピードについていくのには苦戦しました。ですが先生が私の課題図書を一緒に英語レベルに合わせて選んでくれたり、エッセイの修正やコメントで丁寧に今後の課題や強化部分を教えてくれたりと手厚いサポートをしてくれました。
Year11の1年間は通常の英語クラスのみでしたが、Year12ではネイティブの生徒で英語のサポートが必要な生徒達に向けたライティングのコースも通常クラスに加えて受けました。
このコースは8~9週間、週1、2回の昼休みを使いライティングの課題を行うコースです。ここで行った課題は通常の英語クラスで行う課題と同じ扱いで採点されるためこのコースを頑張ると成績が上がります。
Year12までは英語が必須なので生徒は英語の得意・不得意に関わらず全員、英語の授業は同じなのですが、最終学年のYear13では英語の授業も選択制になります。
そのためESOL以外の英語の授業が3つに分かれ、そのひとつが英語が得意ではない生徒に向けた授業でした。この授業の特徴として、
1.年度末テストよりも授業内課題の比率が多い
2.シェイクスピア英語を扱わない
3.クラス担当の先生と別にサポートの先生が週2回手伝いに来てくれる
等があります。
私はYear13でこの英語が得意ではない生徒向けのクラスを選択しました。選択理由は年度末のテストの限られた時間ではクオリティが高いエッセイを書くことが難しかったのと、シェイクスピア英語がとても苦手だったためです。
この授業の課題は別の英語クラスと同じなので授業選択で高校の成績に影響がでることはありませんでした。
このようにESOLが終了した後、すぐに完璧にネイティブと同じとはいかないですが、英語の先生も学校側も様々な形で英語のサポートをしてくれます。
また、生徒が必要だと思えばESOLを卒業可能レベルに達してもESOLを続けることが可能なので皆さんの状況に合わせて学校の先生に相談してみて下さい。
吸収力が高い子供たちでも留学や移民してきたばかりで言語の壁がある時に全て自分の力でこの言語の壁を越えなければいけないのと、ESOLで自分のレベルに合わせて言語サポートが受けられるのではとても大きな差が生まれると思います。
私もESOLなしではほぼゼロから4年で英語の授業にもついていけるレベルにはならなかったと思いますし、途中で辛くて英語の習得を諦めていたかもしれません。英語力はもちろん、学習時のメンタルサポートという面でもESOLは英語を母語としていない生徒に大きな意味があると思います。
ほうかごEnglish インターン生 あかり

